七五三のお参りを控えて「初穂料っていくら包むの?」「のし袋の裏には何を書くの?」と迷う方は多いです。
特に初めての七五三では、マナーを間違えてしまわないか不安になりますよね。
初穂料は神様への感謝を表す大切な儀礼だからこそ、きちんと準備して臨みたいものです。
この記事では、七五三の初穂料について金額の相場・のし袋の選び方・表書きと裏書きの正しい書き方を徹底解説します。
さらに、お札の入れ方や渡すタイミング、袱紗での包み方まで網羅しているので、この記事を読めば七五三の初穂料マナーがまるごと理解できます。
迷いなく準備を整えて、お子さまの成長を祝う大切な一日を安心して迎えましょう。
七五三の初穂料とは?
七五三のお参りで欠かせないのが「初穂料」です。
でも、この言葉自体が日常ではあまり使わないので、由来や意味が気になりますよね。
ここでは、初穂料の基本をゼロから分かりやすく解説します。
初穂料の意味と由来
「初穂」とは、その年に初めて収穫された稲のことを指します。
昔の人は、豊作を願って神様にその初穂をお供えしていました。
これが時代を経て現金に置き換わり、祈祷の謝礼として渡すようになったのが初穂料です。
つまり初穂料とは「神様への感謝をお金に託したもの」なのです。
七五三のお参りでは、この初穂料を神社に納めるのが慣習となっています。
初穂料と玉串料・祈祷料との違い
「初穂料」と似た言葉に「玉串料」や「祈祷料」があります。
どれを使えばいいのか迷った経験はありませんか?
違いを整理すると以下のようになります。
| 言葉 | 主な使い方 | 場面 |
|---|---|---|
| 初穂料 | お祝い事の祈祷での謝礼 | 七五三、安産祈願など |
| 玉串料 | 榊(さかき)を神前に供える代わり | 慶事・弔事どちらにも使える |
| 祈祷料 | お寺で祈祷を受けるときの謝礼 | 厄除け、法事など |
七五三は「お祝い事」なので、必ず『初穂料』と書きましょう。
一方で、お寺にお願いする場合は「祈祷料」や「御布施」と書くのが正しい作法です。
七五三の初穂料の金額はいくらが目安?
七五三のお参りを控えていると「初穂料っていくら包めばいいの?」と悩みますよね。
実は金額に厳密な決まりはなく、神社や地域の慣習によっても異なります。
ここでは、多くの家庭が参考にしている相場と注意点を解説します。
一般的な相場と神社ごとの指定金額
七五三の初穂料は5,000円〜10,000円が一般的な目安です。
特に多いのは「5,000円」か「10,000円」で、どちらを選んでも失礼にはあたりません。
ただし、神社によっては「祈祷料◯円」と指定金額が掲示されている場合もあります。
その際は必ず神社の案内に従いましょう。
| 人数 | 目安金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 子ども1人 | 5,000円〜10,000円 | 神社の公式サイトや受付で確認 |
| 子ども2人(兄弟姉妹) | 10,000円〜20,000円 | 一人分ずつ包むか、まとめて包むか神社に確認 |
大切なのは「金額そのもの」より「感謝の気持ちを込めて準備すること」です。
兄弟姉妹で祈祷を受ける場合の注意点
きょうだいで一緒に祈祷をお願いする場合、初穂料は人数分を用意するのが基本です。
例えば、1人につき5,000円が目安なら、2人なら合計1万円を包みます。
ただし、神社によっては「きょうだいは1袋にまとめてOK」としているところもあります。
不安な場合は事前に神社へ問い合わせておくと安心ですね。
初穂料を包むのし袋の選び方
初穂料を準備するときに「どんなのし袋を使えばいいの?」と迷う方は多いです。
のし袋はスーパーや文房具店でも種類豊富に売られているので、正しく選ばないとマナー違反になることもあります。
ここでは七五三にふさわしいのし袋の選び方を整理してみましょう。
蝶結びと結び切りの違い
のし袋の水引には「蝶結び」と「結び切り」があります。
蝶結びは「何度あってもよい」という意味を持ち、お祝いごと全般に使われます。
一方で結び切りは「一度きり」という意味があり、結婚式や弔事に使うものです。
七五三は繰り返してよいお祝い事なので、必ず蝶結びを選びましょう。
金額によるのし袋の選び分け
のし袋は包む金額によって適切な種類があります。
簡易タイプから華やかなものまで幅広いですが、目安を知っておくと安心です。
| 金額 | のし袋の種類 | ポイント |
|---|---|---|
| 〜5,000円 | 封筒タイプ(シンプルな紅白蝶結び) | カジュアルで一般的な七五三に最適 |
| 10,000円前後 | 水引付き祝儀袋 | 少し豪華さを出して感謝の気持ちを表す |
| 20,000円以上 | 飾り付きの正式なのし袋 | 格式を重んじる場合や特別な祈祷時に |
迷ったら「金額に合ったシンプルな蝶結び袋」を選べば間違いありません。
見た目の派手さよりも、清潔感や丁寧さを意識することが大切です。
初穂料ののし袋の正しい書き方
のし袋を用意しても「表には何を書く?裏はどうする?」と迷ってしまうことがあります。
ここでは、七五三で使う初穂料の表書きと裏書きのルールを、分かりやすくまとめました。
実際のマナーを知っておけば、当日も安心して準備ができます。
表書きは「初穂料」か「御初穂料」
のし袋の中央上段には「初穂料」または「御初穂料」と書きます。
毛筆や筆ペンを使うのが望ましいですが、最近は筆ペンでも十分です。
水引の下段には祈祷を受けるお子様のフルネームを書きます。
両親の名前ではなく必ずお子様本人の名前を書くのがルールなので注意しましょう。
子どもの名前の書き方と連名のルール
お子様が兄弟姉妹で祈祷を受ける場合は、連名で名前を書きます。
たとえば「山田 太郎・花子」というように、左から年長の子ども順に書くのが一般的です。
連名にするときは親の名前は不要で、子どもだけを書くことを忘れないでください。
裏書きの正しい書き方(中袋あり/なしのケース別)
裏面の書き方は、のし袋の種類によって変わります。
次の表で整理してみましょう。
| のし袋の種類 | 書く場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 中袋あり | 中袋の表面中央 | 金額を漢数字(例:金五千円、金壱萬円) |
| 中袋あり | 中袋の裏面 | 郵便番号・住所・子どもの名前 |
| 中袋なし(封筒タイプ) | 袋の裏の左下 | 右に金額、左に住所と名前 |
金額を書くときは、数字ではなく旧字体(大字)を使うのが正式です。
例えば「1万円」なら金壱萬圓、「5千円」なら金伍仟圓と書きます。
裏書きは神社の人が確認する部分なので、丁寧に書くことが大切です。
お札の入れ方とマナー
初穂料を包むときに意外と迷うのが「お札の入れ方」です。
表と裏、肖像の向きなどにルールがあるので、きちんと確認して準備しましょう。
ここでは、初穂料にふさわしいお札の選び方と入れ方を解説します。
新札を用意する意味
初穂料にはできるだけ新札を用意するのがマナーです。
新札は「清らかな気持ちで神様に捧げる」という意味が込められています。
しわや汚れのあるお札は避けましょう。
どうしても新札が手に入らない場合は、折れ目や汚れのない綺麗なお札を選べば大丈夫です。
お札の向きと揃え方
お札をのし袋に入れるときは肖像のある面を表側に向けます。
つまり、のし袋の表書き(「初穂料」と書いた面)を開けたときに、人物の顔が上に見える状態です。
この向きに揃えることで「相手に失礼のない丁寧さ」を表せます。
| 入れ方 | ポイント |
|---|---|
| 肖像面を表に | のし袋の表書きと同じ方向に揃える |
| お札の上下 | 人物の頭が上になるように入れる |
| 複数枚入れる場合 | すべて同じ向き・同じ方向に揃える |
お札をバラバラに入れるのは見た目も悪く、神様に対して失礼にあたります。
「きちんと揃っていること」が最も大切なので、最後に必ず確認してから封をしましょう。
初穂料を渡すタイミングと所作
初穂料を準備しても「いつ、どこで渡せばいいの?」と迷う方も多いです。
神社ごとにルールが少し違うので、事前に確認しておくと安心ですね。
ここでは渡すタイミングと、実際の所作の流れを整理しました。
神社で渡す場所と流れ
多くの神社では、祈祷の申し込み時に初穂料を渡します。
社務所や祈祷受付が設けられている場合が多く、申込用紙を記入して一緒に渡すのが一般的です。
一方、小さな神社では本殿近くで直接渡す場合もあります。
「祈祷の前か後か」は神社ごとに異なるので、公式サイトや電話で確認しておきましょう。
| 神社の規模 | 渡す場所 | タイミング |
|---|---|---|
| 大規模神社 | 社務所や祈祷受付 | 申し込み時に渡す |
| 中規模神社 | 祈祷受付または本殿前 | 祈祷前に渡すのが一般的 |
| 小規模神社 | 本殿近く | 祈祷後に渡す場合もあり |
袱紗(ふくさ)の包み方と扱い方
初穂料をそのままバッグに入れて持ち運ぶのはマナー違反です。
正式には袱紗(ふくさ)という布で包んで持参します。
袱紗に包むのは、のし袋を汚さないためでもあり、相手への敬意を表す意味もあります。
包み方は次の流れです。
- 袱紗をひし形に広げ、中央にのし袋を置く
- 左 → 上 → 下 → 右 の順に折って包む
- 受付で渡す直前に袱紗から丁寧に取り出す
また、渡すときは「よろしくお願いします」と一言添えると、より丁寧な印象になります。
七五三の初穂料で気をつけたいポイントまとめ
ここまで七五三の初穂料について詳しく見てきました。
最後に、準備やマナーで特に大切なポイントを整理しておきましょう。
この章だけ読めば、全体の復習にもなります。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| のし袋の種類 | 紅白蝶結びを選ぶ(結び切りはNG) |
| 表書き | 「初穂料」または「御初穂料」と書き、お子様の名前を記入 |
| 裏書き | 中袋あり → 金額と住所を中袋に / 中袋なし → 袋の裏左下に記入 |
| 金額 | 相場は5,000円〜10,000円(兄弟姉妹は人数分用意) |
| お札 | 新札を用意し、肖像を表に揃える |
| 渡し方 | 袱紗に包んで持参し、受付で「お願いします」と添える |
まとめると、大切なのは形式よりも「感謝の心を丁寧に表すこと」です。
のし袋や金額に気を配るのはもちろんですが、一番大事なのは「お子さまの健やかな成長を願う気持ち」です。
その思いが伝われば、きっと神様にも届くはずですね。
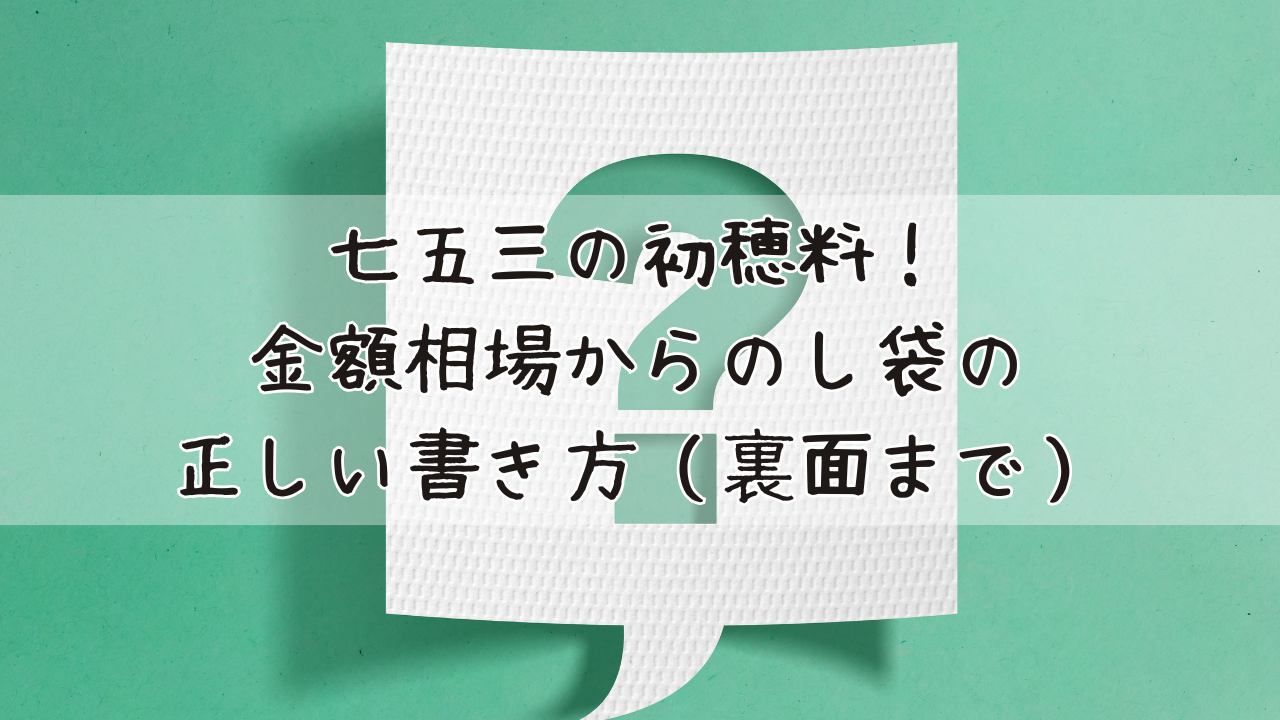
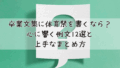

コメント